
ルールの最小化で創造性を導く、インフラ構築を
NODE コンサルタント
フロントオフィスとバックオフィス。企業の前線と後衛は見ている景色が異なるもの。そんな両極に一人で立ち、顧客企業やNODE自体の土台を1段階高めることが、西澤篤央の仕事です。
「長期的に見て、どんな価値が残るのか」と考え、求める成果に辿り着くためのルートを探す発想は、長年プレーしてきたボードゲームでつちかったものでした。
ボードゲームに見立てたルールとロールの連動性

Q 西澤さんは、ボードゲームの日本代表だったんですよね?
はい、ドイツで生まれた「カタン」というゲームです。現在もドイツでは世界大会をやっているのかな。国を超えて「あいつはすごかった」と意識し合うような経験もあります。幸い、日本はどんなボードゲームでも強いんです。「モノポリー」は特に有名ですが、「カルカソンヌ」というボードゲームの大会でも、日本は常連国ですよ。
Q これまでに何種類くらいのボードゲームをしてきましたか?
5桁まではいっていないと思うけど、少なくとも4桁まではやっています。
Q 数千ですか。すごい数ですね。なぜ、そこまで興味を持つことができたんでしょう。
なぜでしょうね。気づいたら……でも、そこは仕事の話にもつながるんですよ。
最終的にはルールや仕組みにずっと興味があるのだと思うんです。仕事も、ゲームに見立ててから考える人間なので、ある仕事にはどんなルールがあるのだろうとか、この人は勝利条件をどう考えているんだろうとか、そこから逆算して最適値のルートを導いていきます。ただし、ビジネスには解明されていない、言語化されていないルールが非常に多い。そんな仕事にたずさわった時に最適値のルートを導き出すのに有効なルールを探り出せると感動します。こんなルールがあったんだと。
Q それは、ルールが開示されていないゲームもやってきたということですよね。
僕自身が好きなゲームはそっち側なんですよ。時間との競争で、部分的な情報や限られたリソースを渡されて、制限時間内に一番最適化した人が勝つ。ルールの一部が各プレーヤーに配られていて、交渉で手に入れたり、断片的なルールを推測しながらリソースをマネージメントしたりするゲームです。
それは、普段の仕事も同じじゃないですか? 例えば、ある仕事を担当した場合、その担当者には任された仕事のルールだけが開示されていて、仕事内容にリソース最適をして働くわけです。けれど、他の人の仕事にまつわる情報が入ってくると、ルールはポンと増える。それに基づいてまたリソース最適化すると、働きも変化していくじゃないですか。
仕事のクリエイティビティを落とさないルール作り

Q NODEでは、どんな仕事をしていますか?
だいたいですが、フロントオフィスが3割、バックオフィスが7割です。今、バックオフィスを移管またはアウトソーシングしている最中ですが、人事周り以外の経理、総務、労務などを全部やっています。
例えば、どんなオフィスツールを導入しようかと考えた時に、「こんな世界を実現したい」という話は必ず出てくるので、それを実現するために必要な思想をともなっているように見えるツールから、何をどう区切って自社のインフラに取り入れるのかを考えるようなことです。
Q ツール選定ひとつをとっても、ゴールへの最適化を図るんですね。それにしても、業務範囲の広さから何でもさばける人という印象を受けました。
うーん、さばくまではいけていません。得意不得意はあります。例えば、銀行に支払いをする場合、自由にできないことも少なくないんです。僕もまだ知らない部分は多いんですが、最後の最後に法律のようなルールに従って動くための制限があって、「このルールで動かなければいけない」という拘束に引っ張られるんですよ。その「動かなければいけないとするルール」を解明できれば、どんな順番で何をしていくべきか逆説的に取るべきコマンドが出せると思うんですが。
Q そのようにルールを踏まえて最適な手順を取ろうとすることは、仕事で最も大事にしていることですか?
いいえ、結果論です。大事にしているのは、コマンドを削ることができるかどうかですね。ルールがあると話しましたが、中には、しがらみ的に残っているだけで実際には必要ないルールも多い。だから、本当に必要なルールは何か、限界まで削ることによって、業務の全体量を最小化して、かつ、やりたいことができるようになる状態は何かを考えています。それは悩み事でもあり、実現したいことでもあるんです。
Q ルールを増やすよりも減らすことのほうに、悩みとさえ言ってしまえるほどの思い入れがあるんですね。
ルールを増やすのは、簡単な解き方なんですよ。でも、その結果、「人がどんどん苦しくなっていく世界」ができていく。ルールがあるかもしれないという不安に追い込まれるからです。ルールが最小であれば、それだけ行動が制約されません。なので、創造的な仕事がそのままできるようになる。仕事としてのクリエイティビティをどれだけ落とさないようにインフラを整備するかは、僕の考えとして深いところにあります。
ルールの最小化を目指す本当の理由

Q 仕事の7割をバックオフィスに割いているので、みんなに対して創造的な仕事ができる環境をつくりたいということですよね。
やっぱり結果として、誰も不幸にならず幸せな成果が出るといいんです。プロジェクトのメンバーが体調を崩すなど、いろんな形でマイナスが発生すると不幸じゃないですか。頑張って成果を出そうと、目的に向かってみんな走っているわけだから。そのために改善することは必ずやっていって、結果的に、みんながうまくいったり、モチベーションが上がったりすると嬉しいです。
Q それをあくまでもインフラとして、みんなには手元にあるのが当然のものに仕上げているわけですよね。
それが一番理想です。褒められるっていうのも逆に、期待値を超えすぎている可能性があるので、難しい。
昔、僕がゲームサークルを運営していた時に鉄則にしていたことがあるんです。何かっていうと、ゲームサークルのお客様の満足度を80点にするということ。肝は60点以下じゃないってことと、90点以上じゃないっていうことの2つです。60点以下っていうのは絶対にダメだってわかりやすいですよね。でも90点以上になってもいけなくて、それはスタッフが疲弊するからなんですよ。お客様とサービスを提供する人、全員がよくないとビジネスって回らないと考えています。
ただ、僕自身は今、インフラから越えることにチャレンジしているんです。3割はフロントオフィスに入って、プロジェクトも担当している。成果を出すのは当然のことだけれど、裏ではフロントオフィスの経験を踏まえて、バックオフィスにおいての改善点も考え、結果的に担当した会社やみんなの仕事が1段階よくなることを目標にしています。
Q これまでの話を振り返ると、西澤さんは仕事を通じて関わる人が創造的に仕事をできて、かつ、その効果が長期で残るものにたずさわりたい方なんだと思いました。なぜですか?
そもそも、「みんな良いことをやりたいはず」って、なぜか勝手に思っているんですよ。ただ、それを実現するのが難しいから、結果としてそんなに世の中に出ていないんだろうくらいに感じています。だから、そんな仕事の発生頻度や発生したものの成功頻度が少しずつ高まると、結果的に良いものが出てきたり、良いチャレンジが生まれたりする社会に変わっているはずですよね。そんな社会のほうが、僕は楽しいって思うんです。
西澤 篤央(Atsuhisa Nishizawa)
1975年、三重県生まれ、千葉・東京育ち。東京工業大学化学科を卒業し、外資系IT会社に入社。その後ボランティアでボードゲームの普及やテスターとしてカードゲームの作成に携わったのちにコンサルティング会社のIT部門のリーダー・管理職に転職。2019年9月に株式会社NODE入社。仕事でゲームをする日々。
| 活躍するメンバー

企業変革のために、人の「NODE」をつなぐ流儀
金 均
代表取締役

諦めず、泥臭く。クライアントとユーザーの幸せを求めて
合田 未怜
NODE 取締役 コンサルティング事業担当

約束以上の成果を。もがいて見つけた一つの答え
豊永 泰士
シニアディレクター

ミッドライフクライシスに葛藤しつつ、価値創出に力を尽くす
細井 睦弘
マネージャー

立場を越えたアイデアで、顧客を幸せにするサービスを
伊藤 英里
マネージャー

話術が得意の営業から、飛び込んだコンサル道
栗原 賢
ディレクター

未体験の挑戦を続けて、自己の可能性を広げていく
森 ゆき
Webディレクター

コンサルの世界で、見習いからコンサートマスターへ
山内 健太郎
ディレクター

立ち止まらず手を動かし続け、前へ進んでいく
田中 駿祐
ディレクター

高い視座と深い思考力、自分の強みを求めて
伊藤 翔一郎
ディレクター

物事の本質を見つめ、良い社会を作っていく
谷相 圭一
マネージャー

考え抜き、経験を積み、勝率を上げていく
加藤 拓斗
マネージャー
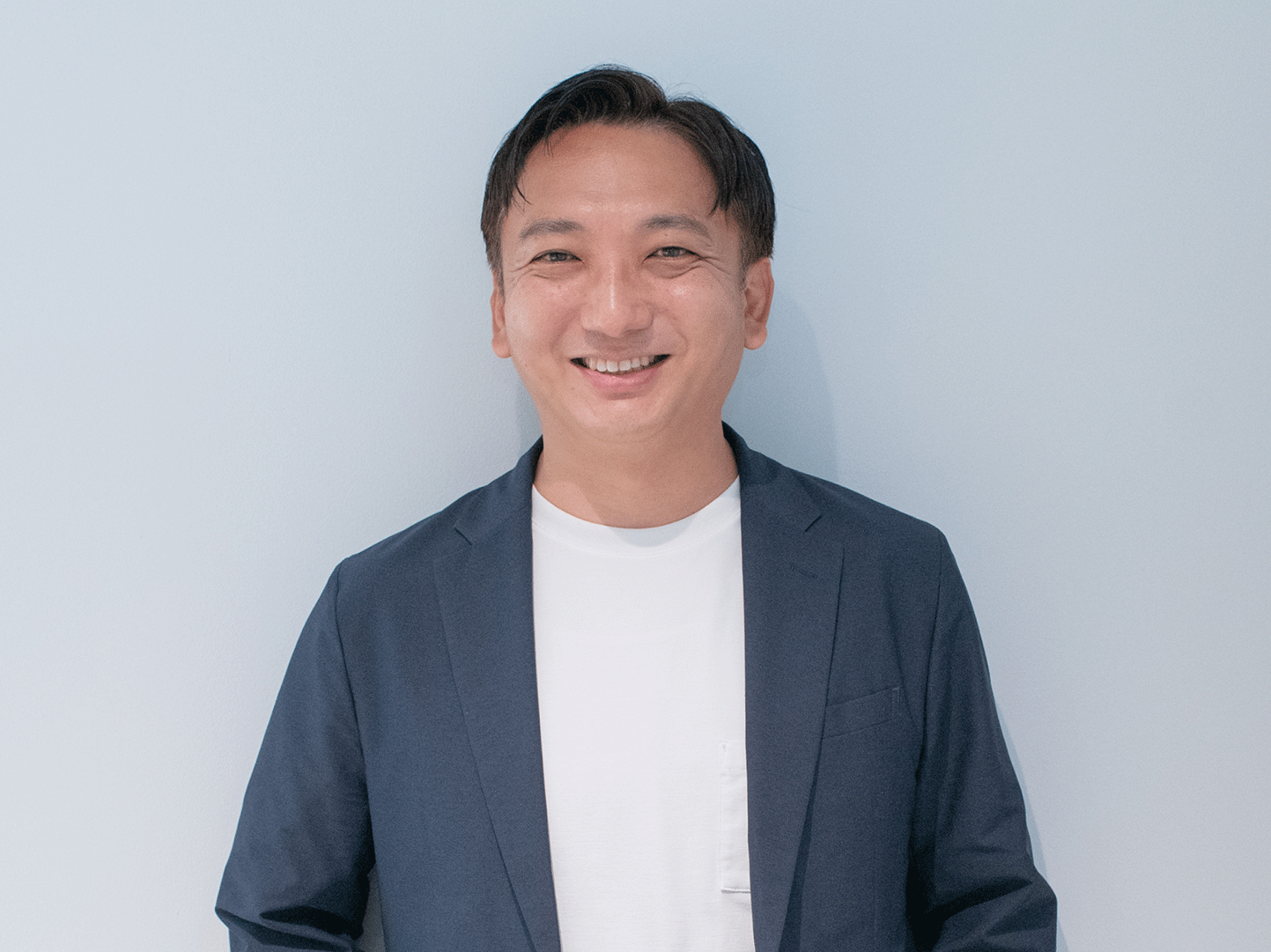
「なかった頃には戻れない」という物やサービスを世に出すために
石田 直行
ディレクター

おしゃれなものの社会的価値を上げる第一人者になりたい
市川 由佳
コンサルタント

チームや事業をリードできる人材になりたい
米川 諒
シニアコンサルタント

目標は「この人がいれば何とかなる」と頼られる人
野口 明日香
CX/UXデザイナー

顧客に誠実に、本質的な課題解決をしていきたい
井上 亜美
コンサルタント

デザイン思考を実践し、仕事と人の縁をつないでいく
足利 洋城
シニアコンサルタント

思考と経験を積み上げ、いつか夢をかなえる
林 美雨
コンサルタント

人のサポートをしたい。常に成長し続けていたい
嶋村 知美
アクセラレーター

新しいことに挑戦して、仕事にワクワクしていたい
竹澤 幸
アクセラレーター
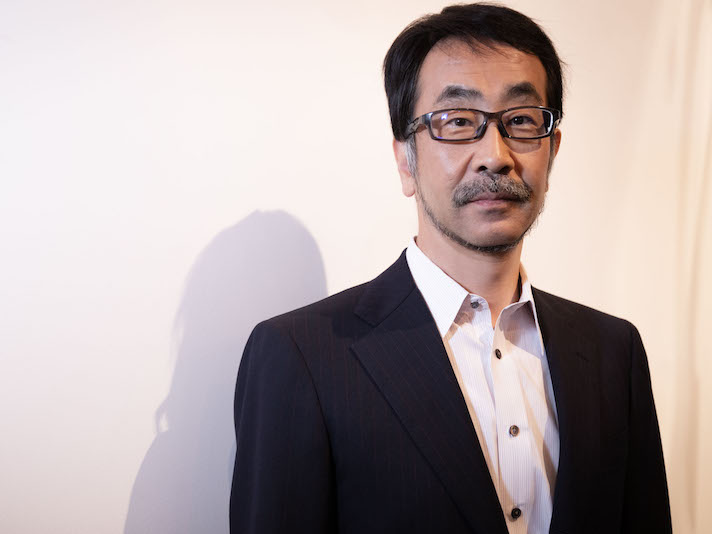
情報、人、会社、そして歴史をつなぐ観察眼
相澤 利彦
顧問・イノベーションプロデューサー

人に価値をもたらす最後の一手はカルチャーを生み出す力
竹内 崇也
エグゼクティブディレクター

複業を楽しくするニュートラルな選択
堀込 泰三
客員ディレクター

人と環境の間に生まれる意味を、コミュニティにつなぐ
前田 俊幸
コンサルタント
幅広く対応させていただきます。
まずはご相談ください。