
立場を越えたアイデアで、顧客を幸せにするサービスを
NODE コンサルタント
NODEはクライアント企業に伴走して、顧客が喜ぶ新サービスを日々考え、生み出しています。手がける数々のプロジェクトの現場に足を運ぶと、クライアント企業をはじめ、専門分野のプロフェッショナルが集い、切磋琢磨する様子を窺うことができます。お互いがお互いの専門領域を超えて、顧客の人生が豊かになることを願って働く。NODEの伊藤英里も、そんなメンバーの一人です。
決まった答えの先へ向かいたい

Q NODEに入ったきっかけは?
前職で代表の金さんと一緒に働いたことがありました。私がビジネスパートナーとしてクライアント先に常駐し、クライアントと一緒に問題解決をする仕事をしているその中で、金さんの働く姿を見たんです。そして組織の垣根を越えたサービスづくりをしたいと思っていた私は、その後に金さんの創業するNODEでのプロジェクトの仕事を魅力的に感じるようになりました。
自社から離れてクライアント企業に常駐していると、常駐先の人として働くことになるじゃないですか。そうすると、常駐企業のルールや習慣に沿ったアイデアが通りやすくなります。私はサービスを利用する顧客にとって、もっといいものをつくりたいと思っていました。そんな時にNODEが実践している顧客志向のコミュニティ型支援のプロジェクトは理想に近いものだったんです。
Q なぜクライアント企業の視点でサービスを考えることに違和感を覚えたんでしょう?
企業の目線だけになってしまうと、どうしても「うちの会社にとって利益が出やすいサービスはこれだ」というアイデアになりがちなんです。「顧客向けにはその選択をしたほうがいいのはわかるけど今すぐには難しい」という制約だったり社内事情だったりする縛りがあることは理解していますが、それだとサービスを利用する顧客にとって本当にいいものに仕上がっていかないんじゃないかとモヤモヤしていました。
Q なぜ伊藤さん自身は、顧客を第一に考えるようになったんだと思いますか?
最初に着いた仕事の影響かもしれません。前職の会社に新卒で入社してから約3年半、インサイドセールスとカスタマーサポートを行うコールセンターで、プレイヤーとマネジメントをしていました。顧客の声が届く場所にいて、生の声を多く目にしてきて、多くの要望がある一方で会社としては対応しにくい状況を見てきたことが大きいと思います。たとえばクレームが届いた時に、会社としてあらかじめ用意していた回答を返すことしかできないのが、歯がゆかったんですよ。
立場を越えたアイデアで価値を生みたい

Q NODEではどんな仕事をしていますか?
2020年3月に入社して半年経ちますが、クライアント企業とともに考えた仮説に基づく顧客調査や検証をメインで担当しています。クライアント企業と話し合う時は、どうしても企業目線に寄ることになるので、調査・検証を通して顧客目線を忘れずに踏まえて、そこにNODEとしての客観的な目線も意識しながらクライアント企業に提言していくことが大事だと思っています。
Q 入社して半年が経ち、NODEの仕事にどんな感想を持ちましたか?
クライアント企業だけでなく、他の協業パートナーとも同じプロジェクトメンバーとして新しいサービスをつくっていくところが面白いなって思います。一般的にはプロジェクトの中でも自分の担当した範囲の仕事をするものだと思うんですが、NODEのコミュニティ型の変革支援では、全員がプロジェクトの目的達成をゴールにしているので、時に担当業務の範囲を超えて、進行が遅れているところがあったら手が空いているメンバーでサポートするように働くこともあるんです。それぞれの所属する会社や担当といった枠を越えて協働できるところが魅力的ですよね。
もちろん、仕事が遅れてしまった会社や担当者は責任を問われるんですよ(笑)。だから、厳しい面もあるんですが、それだけで終わることがなくって、プロジェクトが進むようにお互い支え合うところが好きなんです。いや、でも「自分の担当はこの仕事だから他は手伝いません」って言えたほうが楽ではあるんですけど。そういう意味だと、大変にもなったのかもしれませんね。
Q 一つの企業や担当といった枠を超えて、アイデアや仕事を進めていくことに伊藤さんは魅力を感じています。なぜでしょうか?
うーん…何ですかね。意見を言いやすい環境に魅力を感じているのは、プロジェクトに関わるメンバーが不満を抱えて働かないほうがいいと思っているのと、陰口を言うよりも表で伝えたほうがいいことが多いと思っているからかもしれません。直したほうがいいことがあったら、直接聞けると直せるじゃないですか。それがいい方向に進むきっかけになるかもしれませんし。
あとは年功序列みたいに、硬く決まってしまっていることが好きじゃない部分もあります。若い人でも実力を示していけたら会社にとってもサービスにとってもいい結果が残るかもしれないって思っているんです。だから、NODEのインターンの子たちにとっても、意見の言いやすい環境になったらいいなって、何となく言いづらそうに見えた場合は代わってアイデアを伝えるなどしています。
顧客に真っ直ぐに向き合える場所で頑張りたい

Q クライアント企業の目線に他のプロジェクトメンバーの目線が入ったほうがいい結果が残る、と思うのはなぜですか?
一つの会社に長くいると、同じやり方で凝り固まっちゃう部分はあると思っています。新しく入ってきた人や第三者が言った、ちょっとしたアイデアがそんな状態をほぐすことになるんじゃないかって感じるんです。だから、新しい意見を取り入れたいですし、私自身も自分の固定観念がほぐれる時もあります。
もちろん、新しいアイデアが入った上で、それまでクライアント企業がやってきたことの延長線で話が進むこともあるんですよ。でも、その延長線は新しいアイデアが入った上で進んだ結果だから、顧客にとって結果がよくなる進行だと思うんです。
Q クライアント企業に新しいアイデアを受け入れてもらうことって大変そうな気もしますが、うまくいかない時に息抜きすることはありますか?
今はオンオフを分けないで、休みの時期に勉強したり進めておきたい仕事をしていることのほうが好きなんです(笑)。それに私にとってはいろんなことに携わりたいっていう気持ちが大前提にあって。その上で、関係者が気づいたアイデアを何のしがらみも気にせずに言えて、顧客が喜ぶサービスをつくっていける時間を過ごすのが理想です。今はまだ新しいサービスをリリースするところまでしか経験できていないので、これから顧客が喜ぶ様子を見るのが楽しみの一つになっています。
Q 何かつくりたいサービスはありますか?
それが特にないんですよ。抽象度が高いんですけど、やっぱり顧客が喜ぶサービスをつくる仕事がしていきたいです。多分、飽き性なんです。だから、一つのことをずっと続けていくよりも、クライアント企業や協業パートナーと一緒にプロジェクトを進めて、いろんな新しいサービスをつくっていくNODEでの仕事が好きなんだと思います。
Q 最後に、伊藤さんにとってNODEはどんなところなのか教えてください。
私にとってですか、そうですね…。「顧客にとって、新しいサービスをいいものにつくっていきたい」っていうゴールがあって、そのゴールに妥協しない人たちが集まっているところですかね。私自身も妥協しない環境にいるから、頑張れるって思うんです。
伊藤 英里(Eri Ito)
1993年、福島県生まれ。成蹊大学理工学部物質生命理工学科を卒業。白衣を着るかっこいい研究職を目指していたが、様々な出会いにより、困っている人に寄り添う仕事をしたいと思うようになり、業務プロセスコンサル・ICTアウトソーシングの会社に新卒入社。人がもっと自分らしく幸せに過ごせるよう、より本質的な問題解決を手掛けたいと悩んでいた時に代表の金と出会い、現在に至る。
ハマっているのは、岩盤浴や銭湯、お寺でのマインドフルネス。仲間とおいしいごはんとお酒を囲むのが憩いの時間。
| 活躍するメンバー

企業変革のために、人の「NODE」をつなぐ流儀
金 均
代表取締役

諦めず、泥臭く。クライアントとユーザーの幸せを求めて
合田 未怜
NODE 取締役 コンサルティング事業担当

約束以上の成果を。もがいて見つけた一つの答え
豊永 泰士
ディレクター

ミッドライフクライシスに葛藤しつつ、価値創出に力を尽くす
細井 睦弘
コンサルタント

話術が得意の営業から、飛び込んだコンサル道
栗原 賢
コンサルタント

未体験の挑戦を続けて、自己の可能性を広げていく
森 ゆき
ウェブディレクター

コンサルの世界で、見習いからコンサートマスターへ
山内 健太郎
コンサルタント

「仕事って愛なんだよね」15年越しに実感した真実
松本 裕代
コンサルタント

立ち止まらず手を動かし続け、前へ進んでいく
田中 駿祐
コンサルタント

高い視座と深い思考力、自分の強みを求めて
伊藤 翔一郎
コンサルタント
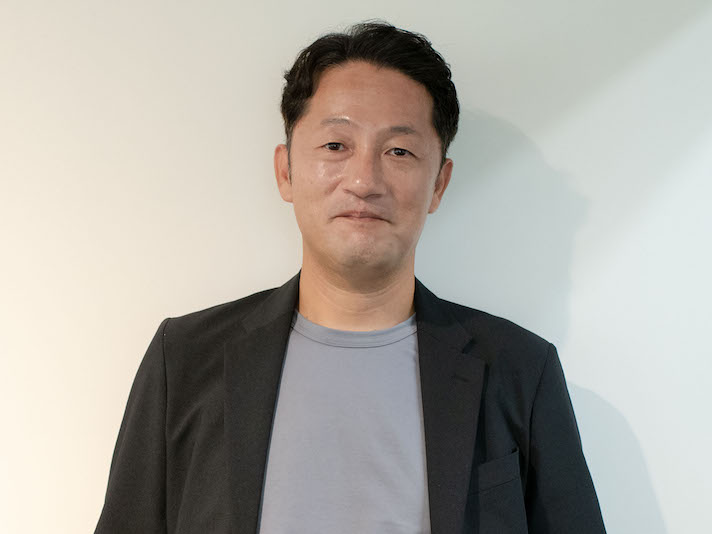
NODEコミュニティという面白い船に乗っていたい
林 賢介
セールス統括・ディレクター

物事の本質を見つめ、良い社会を作っていく
谷相 圭一
コンサルタント

考え抜き、経験を積み、勝率を上げていく
加藤 拓斗
コンサルタント

状況は変わる、変えられる。
だから諦めず、粘り強く前へ
田中 大生
コンサルタント
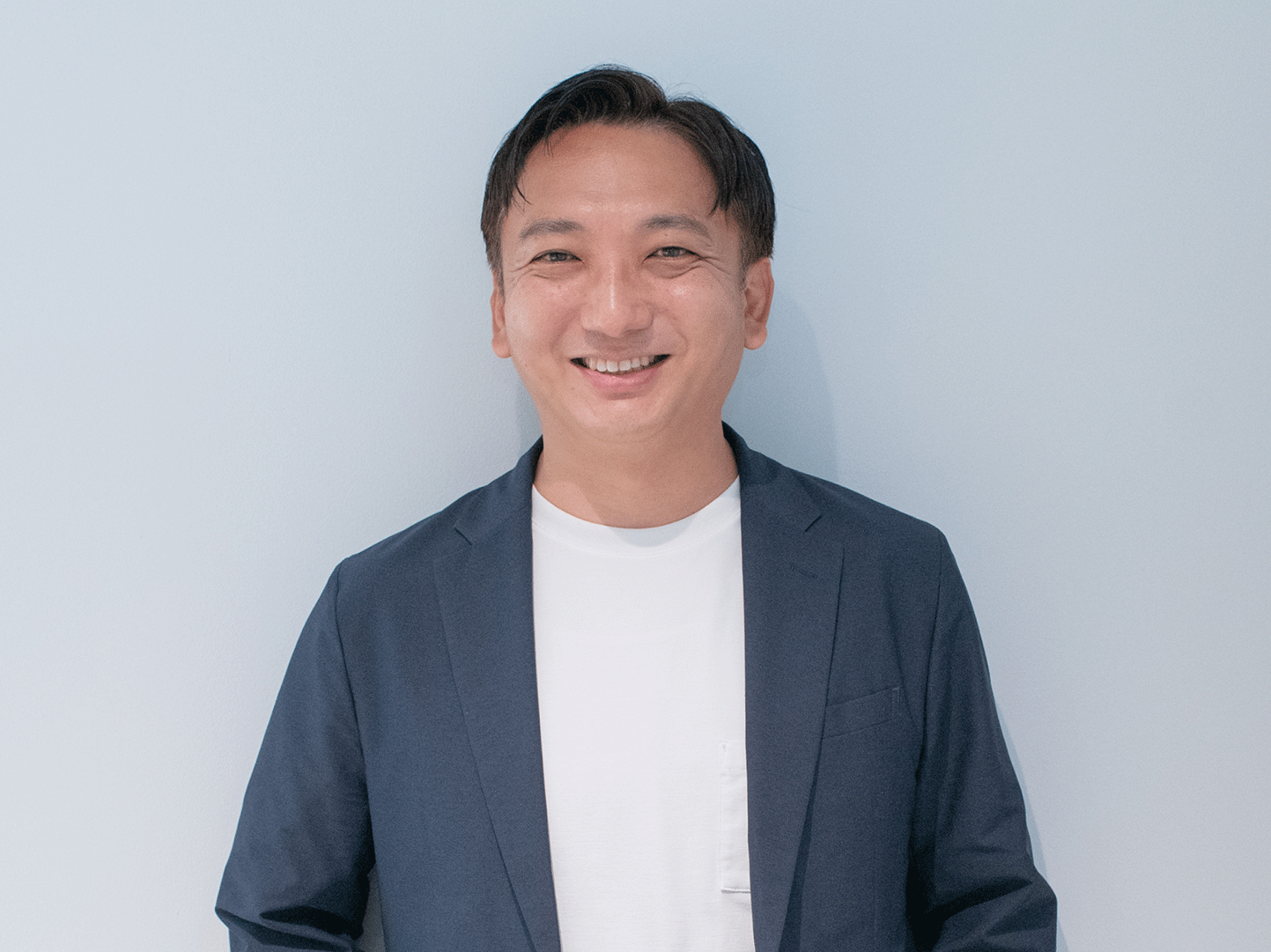
「なかった頃には戻れない」という物やサービスを世に出すために
石田 直行
コンサルタント

おしゃれなものの社会的価値を上げる第一人者になりたい
市川 由佳
コンサルタント
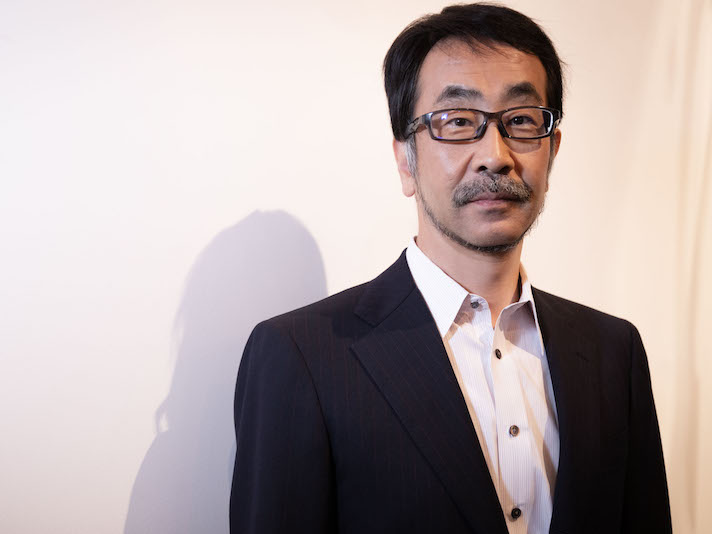
情報、人、会社、そして歴史をつなぐ観察眼
相澤 利彦
顧問・イノベーションプロデューサー

人に価値をもたらす最後の一手はカルチャーを生み出す力
竹内 崇也
エグゼクティブディレクター

複業を楽しくするニュートラルな選択
堀込 泰三
客員ディレクター

人と環境の間に生まれる意味を、コミュニティにつなぐ
前田 俊幸
コンサルタント

ルールの最小化で創造性を導く、インフラ構築を
西澤 篤央
コンサルタント
幅広く対応させていただきます。
まずはご相談ください。